トップ>文献・論文>コンダクターの五感
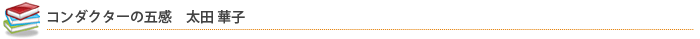
H16「つながりのなかで―芝居をめぐる共同体性の考察―
プレイバック・シアターにおけるコンダクターの役割」抜粋
2.コンダクターの五感
1.司会者、ファシリテーターとして
「場に対する感受性」
コンダクターの仕事としてまず挙げられるのは、その場を遂行する司会者、ファシリテーターとしての役割である。
その要素として、場を進めていく上での判断力、決断力がある。
場の流れを感じとり、今この場で何が起こっているのかを理解すること、そして次へと進むべき方向性を見極める。
これについて羽地は「場に対する感受性」といっている。
今この集団はどういう集団で、なにを必要としているのかを感じとる。
集団は生き物と同じように、生まれてからだんだん成熟していって時に倦怠期があり、老年期があり、終わりがあるというように、ひとつのサイクルを辿るという。まだ集まったばかりの未成熟な集団では、「次にこれをやろう」といった明確な指示はその場を動かすきっかけとして働く。
そして成熟してきたら、自分たちで動くことに任せることが大切な時期もあるのだという。
こうして場の成長段階に合わせてリーダーシップのあり方は変わっていく必要がある。一定のリズムや、一方的な進め方では限界がある。
そういう意味で、いまグループがどういう時期で、なにを必要としているかを見極めることはファシリテーターとしての重要な役割といえる。
「いくつもの気持ち、ひとつの場」
またその場、その集団がひとつの方向に向かうための交渉力は、それらを実行するためになくてはならない能力となる。
これに欠けると、グループはやらされているといった感情や反発を抱いてしまうことになりかねない。
ひとつのグループが同じ考えや波動、気分で進んでいくとは限らない。いや、進んでいくことはまずないだろう。
しかしどんなに正確に判断したところで、グループがその決断を受け止め、ついてきてくれなければ、成り立たないのである。
それぞれの考えや感じ方はさまざまであり、統合していく作業、いわゆるネゴシエーションが必要不可欠となる。
ネゴシエーションとは、「違いを埋めていく作業」であると羽地はいう。
プレイバック・シアターの冒頭で、羽地はよく「さぁ今からのこの時間、みんなで楽しく実りのある時間を過ごしましょう、終わるとききてよかったなという時間をともに過ごしましょう」という。
これも実はすでに大きなネゴシエーションのはじまりだ。
期せずしてそのグループに参加せざるをえなかった参加者であっても、楽しく、来てよかったな、と思いたくない人はまずいないだろう。
そしてコンダクターも楽しい時間をともにつくれたらと願っている。双方の目標を満たした提案である。
いかにお互いの接点、共通の目標を見つける目的を探し出せるかが、このときの重要な仕事となる。
気兼ねして逆に参加者に合わせてしまっては、結果としてその人にとって満足のいくものにはならないという。
また、場全体とのネゴシエーションを要する場面もある。
セラピーなどの場合では、ひとりがトーンダウンすると、それが場全体に伝染するということが起こり得る。
しかしその場合も、「それならなにもやらないで寝ていよう」という選択はあまりにも不毛である。
お互いが無理なく安心して、楽しい時間を過ごすには、そうした交渉の能力と実践が、場を次のステージへと導き出す原動力となる。
どんなグループなのかそうした意味でも参加者との信頼関係を築いていくことは、大きな意味をもつ。
ひとりひとりにフォーカスを当てることによって、お互いの意識をしっかりつないでいく必要があるだろう。
羽地のプレイバック・シアターでは一人一人が主人公になれる瞬間が必ず設けられている。
それは、うそ?ほんと?のような何気ないエクササイズの中に組み込まれているものもあれば、マッピングなどのソシオメトリーを使っていく場合もある。
たとえばオープンのワークショップでは、その日のグループでアクターとして表現したい人もいれば、じっくり自分の思い、時には悩みや問題に耳を傾けたいと思ってやってくる参加者もいる。
その日のプレイバックで羽地は、「表現したい―したくない」を縦軸に、「語りたい―語りたくない」を横軸にとったマッピングを行い、お互いの気持ちを明らかにしていった。
そして常にエッジの人にフォーカスを当てることを忘れない。
エッジ、そのグループにおいて極端な立場の人はよかれ悪しかれ心細く、何らかの特別感、疎外感を抱きかねない。
この場合では、とくに語りたくも表現したくもない不安を抱えた初めての参加者と、元気いっぱい語る気満々、やる気炸裂の参加者とでは遠く距離を隔てることになるだろう。
しかしそうした場における自らの「位置」を確認することで、どのような精神、身体状態であったとしても、自分の居場所を確保ことができるのである。
他にも、疲れている人、とっても元気のある人、場合によっては外国人など言語的不安のある人、身体的ハンディキャップをもつ人など、その場がもつ課題はさまざま想定されるが、ここで何よりも大事なことは、まずグループで、一度その課題にしっかりフォーカスを当てて、みんなで認知するということ。
そして「もう一度ゆっくり言ってください」「休ませてください」「もっとやろう」など、参加者全員がそのグループの中で自由にコメントできる、それにみんなが反応してくれる。
誰一人として欠けることなく前進し、誰もが自分もこのグループを支えている一員なんだと認識することは、プレイバックにとどまらず、まさしく社会における自己存在価値を確立することにつながる、大切な意識である。
違うということの認識は統合の第一歩であるといえるだろう。
そのためにもコンダクターは、今その場にどんな人が集っているのかをみていかなくてはならない。
しかしそこにずっと立ち止まって見ていてはそのグループは停滞してしまう。
その問題をみんなで確認した上で、ギアを入れ替え、前に進めるよう促していくタイミングを計ることも必要である。コンダクターは五感を解放してレーダーを張りながらファシリテートしていく。
2 セラピスト、カウンセラーとして
「ナチュラルメディスンとして」
まずプレイバック・シアター自体の治癒的効果について触れておきたい。
治療としてのプレイバック・シアターの位置付けは、集団療法に含まれる。
集団療法は、サイコドラマ、エンカウンターグループをはじめとし、交流分析、ゲシュタルト療法などでも用いられる治療形態で、複数のクライアントとセラピスト、トレーナー、ファシリテーターなどと呼ばれるリーダーから構成される。
集団療法には大きく分けて2つの性質があり、ひとつは、たとえばサイコドラマなどにみられるように、グループでありながら、その場をひとりの個人に焦点を当てて治療を行なう方法である。
サイコドラマははじめから治療技法として確立された療法なので、ひとりのクライアントに1時間から2時間を費やし、その間、他の参加者もその人の問題解決に協力するといった形を取る契約で進められる。
それと異なりプレイバック・シアターは、まず問題解決が目的ではない、ということが前提にあげられる。
プレイバック・シアターはグループ全体に焦点をあてた「場」である。
その「場」となるグループの全体性、健全性、一体感をもつことが、第一に考えられている。
一人一人が無理なく、安心して場に集えるということがなによりの目的であり、その結果、個人の抱えていた問題の解決がなされることがありうるという、従来の発想とは異なるものであるということを理解しておく必要がある。
というのも、治療、問題解決という概念ではなく、あくまでもアート、エンターテイメントとして生まれたプレイバック・シアターであるといった点から、人間本来が持つ表現性、語ることによる浄化性、そして共同体性がプレイバック・シアターの癒しの姿であるといえるだろう。
「NEEDED」
プレイバック・シアターにおける「支える」という新たな関係性、また役割の交換は治癒的観点からも非常に注目されるところである。
参加者はプレイバック・シアターの中では、誰かの気持ちを誰かが表現する、テラーのストーリーをアクターが演じる、演じられたストーリーを観客として見守るといった、いくつもの関係性の中で、他者を支えるという体験をすることができる。
以前、精神障害者作業所ひあしんすと日本精神保健看護学術学会でプレイバック・シアターを行った際、作業所のスタッフである富田あけみさんは最後のスピーチでこう語った。
「私たちは、いつも看護婦さんやお医者さんに支えられている側だけれども、
ケアする側も様々な問題を抱えながら、自分たちをケアしなくてはいけないことを、ケアされる側も悪いなと感じている。
プレイバック・シアターを通して、そういった役割を超えて関われることで、
いつもケアされる側がケアする側にプレゼントできることがあるということが、よろこびだった。
自分たちにもやれることがある。「与えることによって与えられる。」ということだと思う。」と。
人は、必要とされることを必要とする生き物である。
プレイバック・シアターの中で誰かのために表現するということ、そしてそれを相手が大切に受けとり、喜んでくれるという経験は「大切にされているんだ」「受け容れてもらった」という愛されている実感、また劇や表現を通してプレゼントすることで「自分も人を支えられる」「役に立てるんだ」「自分にもできることがあるんだ」という自己価値感、セルフエスティームにつながる。
そしてそこに生まれるきずなの実感は連帯感や帰属感を満たし、自己肯定感を大きく高めてくれるものである。
そして感じたままに自由に表現できる、いたいようにいることのできる場は、自由に決断できる自律感を与えてくれるだろう。
これらは人間の基本的ニーズ(*2)として、人と人がともある上でもっとも大切な体験である。
プレイバック・シアターのもたらす治癒的効果は、原因を取り除くことでも、問題の根っこを突き止めることでもなく、これらを満たすこと、ただそれだけなのである。
「語ることの不安」
コンダクターのセラピスト、カウンセラーとしての役割は、いわば「集団」に対して「個」ひとりひとりとのかかわりということになる。
これは特にコンダクターとテラーの関係において大切な役割といえるだろう。
プレイバック・シアターで語られるストーリーを用意しているというよりは、その時ふと浮かんだ予期せぬストーリーを語ることがほとんどである。人にはじめて語るストーリーも少なくない。
テラーは語りたいという思い、欲求とともに、語ることへの不安や心細さを併せ持っている。
テラーがグループの中で、時には大勢の中で自らの大切なストーリーを語るということは、内的世界を外界に晒すことであり、日常の生活においてもなかなか語れる場は限られている。
自分のストーリーは人前で語る価値のあるものだろか、取るに足りない、つまらない話ではないだろうかといった不安をもつこともあるだろう。
個人的な体験や思いを外に露出することは勇気がいるし、場合によっては無防備に開いた自分自身が傷つくことへの恐れを抱くこともあるかもしれない。
テラーがコンダクターの前で、アクターの前で、そして何人もの観客の前で、今まさに語ろうとしているとき、そこにはコンダクターのしっかりとした力添えが何よりも不可欠である。
「聞き入れてもらっている安心感」
コンダクターは観客の視線にさらされたテラーをしっかりと守ることが必要である。
それによってテラーは安心して自らの内面に浸れる感覚をもてる。それはその人のストーリー、すなわちテラーの経験や境遇、さらには存在そのものを受け止め、一時的に受容するということである。
それにはプレイバック・シアター独自のコンダクターの位置に注目したい。
カウンセリングにみられるように、多くのセラピーでは治療者とクライアントが対面の面接によって行なわれるものがほとんどである。
しかしプレイバック・シアターでのコンダクティングはテラーの右側に寄り添うようにして進められる。
それはコンダクターがテラーと同じ視線、風景を共有することであり、そこでたとえばコンダクターが呼吸を感じ、テラーと姿勢を合わせることでテラーの気持ちを一緒に味わうことができる。
コンダクターがテラーとともに徹底的にそのストーリーを楽しみ、ワクワクし、時に怒り、いたみ、悲しむことで、テラーは、それが自分では言語化できなかった漠然としている事柄、ひとりでは見たくもない、思い出したくもない封印された体験であったとしても、この人なら一緒に体験してくれるだろうと思えたとき、安心してもう一度追体験することができると羽地はいう。
そして、コンダクターが聞き入れてくれている、気持ちをわかってもらえたという実感は、過去にあったその体験を現在の自分として、改めて語れるのである。
それは、先に述べた姿勢であり、添うということであり、そしてなにより大切なことはコンダクターが自分自身の軸をしっかりと据えておくということである。
横にいてしっかり聞きながらも、コンダクターは決して一緒になってぼろぼろになることはないという安心感は、テラーにとって、非常にこころ強く、安心して自らのストーリーを語ることができると羽地はいう。
コンダクターは常に、共感と共感的理解のバランスをとり、ありのままの自分として一緒にいようとする誠実な姿勢が大切である、と。
「共感と理解」
「同じ気持ちになれない限界をわかっている」という羽地の言葉は、私にとって非常に深く、衝撃的だった。
私は、感じたい、感じようとしたい、感じたつもりでいたいと思っていたかもしれない。
しかし「テラーは共感だけを求めているわけではない」と羽地は続けた。
たとえば悲しみを、本当にそのとき悲しかったんだ、とわかってあげることが、テラーにとって何よりの安心感につながる。
そうしてコンダクターがわかってあげることで、テラーはその感情の存在を認め、自分の気持ちを感じ、しっかりと味わうことができる。
羽地のコンダクティングに、テラーとの距離を感じることはまずない。
そのストーリーをともにに驚き、よろこび、悲しみ、まるで手を携えてその先へと歩みを進めるようである。
「同じ気持ちになれない」。それはテラーに対する誠実さと、尊重がこめられた言葉だった。
わかってもらえると、テラーはもっともっとその時の自分へと掘り下げていく。
微妙な心のぶれ、もっと深くの葛藤までも伝えようと思うものである。
そのつどの言葉に立ち止まり、ともに感じ、ともに味わう。
テラーの言葉を聞いて感じた温度、ゆらめきを感じとり、コンダクターが自らにしっかりとストーリーをめぐらせること。
相手の気持ちを深めることができるということは、きっと自分がどれだけ深く感じとれるか、自分自身の経験が深まっているかであるのだろう。
コンダクターはただ、言葉をなぞるだけでなく、どう聞いたかをテラーに伝え、確認していく必要がある。
人間の自己治癒力には悲しみや傷ついたことを治そうとする瞬間がある。しかし、それはとことん悲しみや、傷ついたことが表出したときにしか沸き起こらないと羽地はいう。
テラーの経験にとことん付き添い、自己治癒力の沸きあがる瞬間にともに立ち会うこと、それがセラピストとしてのコンダクターの大事な仕事といえそうだ。一緒にその先へと連れ出すことも、同じ方向をみているからこそ、できることなのである。
3 アーティストとして
「パーソナルチェンジ」
自分の感情に頓着しないでいると、感情はこころに埋まってしまう。
そうするとその苦しみや悲しみはおろか、輝きもその価値も、感じてあげることができなくなってしまう。
自分なんて取るに足りない人間で、自分が社会にいても誰もふり返ってくれない、泣いても怒っても誰も知らない、自分が死んだとしても、誰も涙しないんじゃないか…感情はますます粗末に扱われ、見失われていく。
プレイバック・シアターを通じて「語る」という行為、また「みる」という行為を経て、テラーの世界観が変わることがあると羽地はいう。
自分の中に埋もれていた感情が言語化され、目にみえるものとして対象化されたとき、はじめてそのものを捉え直すことができるのである。
ブラジルの教育学者パウロ・フレイレは、被抑圧者の識字教育のなかで、文字を獲得することは、自らのおかれた状況を自覚的、主体的に再構成していく「意識化」(*3)であるとし、抑圧者によって奪われた人間の豊かさを取り戻すその概念的手段とした。
「意識化」することは自らの言葉によって「世界を命名する」ことであり、命名された世界を分かち合うことである。
それは自分と自分の対話かも知れないし、あるいはその場に居合わせた者とのコミュニケーションかも知れない。
言葉によって、あるいはからだを使って表現されるということで、人は自分自身に、そして他者に対して伝え、知らせ、訴えかける。
自らのこころを積極的に感じ、その感情をもちだすことは、主体的に生きることへの意識変革であり、それは世界観の変革である。
「誰もが大事な存在であり、かけがえのない人生なんだとみんなが感じてくれたら、こんなに素晴らしいことはない」と羽地はいった。
「ディレクターとして」
プレイバック・シアターはまさしく総合芸術であり、ストーリーを舞台にのせる青写真を描くのはアーティストとしてのコンダクターの仕事である。これはいわば演出、監督的役割ということになるだろう。
アクターの持っている力を最大限に発揮させることもコンダクターの重要な役割となる。
プレイバック・シアターのコンダクティングにはリピートといって、テラーの語ったストーリーを上演の前にコンダクターがもう一度語ることがある。
このときコンダクターは受けとったストーリーを改めてその手からアクターに渡すという意味と、テラーとともにストーリーの構成を確認していくといった意味をもってこの作業を行なう。
場合によってはまったく役者に任せてしまうこともあるが、それでも役者たちはコンダクターから何らかのメッセージを受けとっている場合が多い。
テラーのストーリーが、観客、そしてアクターにしっかりと手渡されるかは、このストーリーテラーとしてのコンダクターの手にかかっているといっても過言ではない。
「ストーリーの昇華」
そして時にはテラーによって語られたストーリーを、観客に受けとりやすくすることが必要なこともある。
プレイバック・シアターで分かち合われるストーリーは気持ちよかった、楽しかったストーリーばかりではない。
もしかしたら辛かったこと、情けなかったことの方が多いかも知れない。
そのような時、観客がそうしたストーリーに対して嫌悪感を抱くことのないように配慮しなければならないだろう。
時にセラピーとして行なわれるプレイバックでは、虐待のストーリーや暴力のシーンが演じられることもある。
誰もが目を背けたくなる光景であるはずだ。
しかしテラーがそのストーリーに囚われ、支配されているとしたら、そのストーリーが語られ、演じられることにきっと意味があるだろう。
そしてもうひとつは、テラーの捉え方に明らかに同意、共感できない場合がある。
「私だったらそんな考え方はしない」「あなたが悪いんじゃないの?」と思わざるを得ないストーリーが語られる場合もある。
しかしプレイバック・シアターでは、そういった批判的意見の発言やフィードバックは行なわないことが原則である。
主観的事実をありのままに、ただ受け止めるだけである。
たとえそうした受け止めがたいストーリーであっても、コンダクターの解釈や聞きとり方、またアクターの演じ方、表現によって受け容れられる可能性は大いにあり得る。
羽地はそれをストーリーの芸術的昇華といっている。そのストーリーの奥底にある普遍的テーマ、さらにその先の本当の気持ちを浮き彫りにしていくことで、そのテーマは観客にも共通に流れる普遍性をもったものへと純化される。
4 ショーマン、エンターティナーとして
「楽しみを分かち合う」
聴くことや受容するといった受動的要素を先に挙げてきたが、コンダクターは聴き手、調整役に徹するわけにはいかない。
プレイバック・シアターは基本的に楽しむ場である。
「ようこそ、皆さんよく来てくれました」コンダクターは最善を尽くしてその場全体が一体となって楽しむ場を提供するショーマン、エンターティナーでもあるのだ。観客と掛け合いながら、常にその反応や場に対する安心感をみながら進めていく。
そのためにも、まずリーダーであるコンダクター自身が、自分のコンディション、状態を知っておく必要があるだろう。
その場に対して極端に緊張していたり、気持ちが高ぶっていたりする場合は特に注意したい。
場の状態、参加者のテンションを感じ取って、歩調やテンポのぶれやズレを調整していく必要がある。
ときにはコンダクター自身が「緊張しています」など自分の状態を明言化することも、場との融合に役立つかもしれない。
自分の緊張をほぐすことがグループの緊張を和らげていくだろう。また相手に同調して楽しめれば、参加者も楽しくなると羽地はいう。
もしその場が沈んでいたら、自分も一緒に沈んだところから同調して、同じリズム感をもちながら、進みたいイメージに半歩先、半歩先へと歩みを進ませる。
同じようでありながら、とどまることなくその理想の状態へと向上させていくのは羽地の得意とするところだ。
自分自身を心地良い状態にもっていくことは、安心と安定感をもってお互いが楽しむ場につながる。
「拠り所をもつ」
コンダクターがどうあるかによってその場の質や意識は変わり、そのあり方がグループ全体のノーム、そのグループがもつ暗黙の構造となる。
しかし経験の浅いコンダクターは、なかなかコンダクティングに自信をもつことができない。
緊張するし、どういたらいいのかすらわからなくなってしまうことがあるかもしれない。
そうした場合も、自分自身でいられる自分の拠り所を明確にもっていることは心強い。
拠り所とは、何のためにプレイバック・シアターをするのか、なにをもってプレイバック・シアターとするのか、つまり自分がプレイバック・シアターの中で何を一番大切にしたいかということである。
そのひとつはプレイバック・シアター全体として、そしてもうひとつは個々のグループに対するもののふたつがあるだろう。
羽地が常に大切にしていることは、人々が集い、ともになにかつながりを感じ合えて、新しいものが生まれる場であるということ。
そして個々のグループとしては、「安心していられること」であったり、「自分らしくいていいんだ」という肯定感をもつことであったり、そのグループの段階や状態に合わせて、より具体的なビジョンをもつ。
自分のやりたいことがはっきりしていると、その場での言葉のテンポや声のトーン、アプローチの仕方はおのずと決まってくる。
なにかひとつしっかりとした志があると、それはコンダクターとしてのモチベーションを保つためにも、自分があり方を見失い、混乱したときの建て直しにも力になってくれる。
「イメージング」
プレイバック・シアターはそれ自体即興性が強く、集まる人のコンディションや、その場の状況でどんなことも起こりうる。
ウォーミングアップの時間や種類、そしてストーリーの流れなどは、始まってみないとわからないということが往々にしてある。
場合によっては人数や対象ですら事前に読めないこともあるだろう。しかし、だからといってすべてをその場に任せたらいいかというと、そうではない。
即興性や柔軟性を十分に楽しみ、発揮するためにも、コンダクターはそのグループのねらいや流れ、そして最終的にどうなったらいいのかをイメージしておいた方がいい。
和気藹々としたグループだろうか、悲しいことを悲しいこととして分かち合えるグループだろうか、それとも、みんなそれぞれが楽しめるグループだろうか。
自分がそのグループにおいてどうあるべきか、またどんなグループにもっていきたいかを思い描いておくことは、たとえその通りにならなくても、事前のイメージを土台に進行状況を確認することができるし、何がどう変わっているのかを明確にすることができる。
5 シャーマンとして
「リチュアルとしての存在」
朝比奈隆はその著書(*4)のなかで、指揮者とオーケストラの関係はあいた相対ずく尽、つまり統一された意志の上で成り立つものだとしている。そこにもし指揮者が付け加えられることがあるとすれば、音楽の速さ、それだけは手の動き通りで指揮者に絶対権があるという。
プレイバック・シアターにおけるコンダクターの絶対権は、リチュアルを通して発揮される。
羽地は「リチュアルとはリズムです」といった。
このリズムが読めないと参加者は真面目な場なのか、気楽な場なのか、集中するのか、楽しんでいいのかわからなくなってしまう。
その場に一定のリズムが流れていることで、参加者はそのリズムに安心して場に身を任せることができるのである。
リチュアルは日常と非日常の境界線であり、また目指している姿を形として表すことである。
コンダクターはこのリチュアルによって、その場で行なわれていることの意味や目的を、言葉よりもダイレクトに、わかりやすい形で参加者に伝えることができる。
プレイバック・シアターの中で何度も繰り返される動きや決まり文句のような言葉は、はじまりと終わり、役割の交換を明確に指示する。
プレイバック・シアターは既成の劇場で行なわれるとは限らず、リビングが、食堂が、時に劇場に変わる。
コンダクターがいかなる状況下においてもしっかりとリチュアルを遂行し、リズムを明確にもつことで、どんな空間にも安定した場を確保し、それを参加者ひとりひとりが感じとることで、同じ意識を共有することができる。
そのためにも、コンダクターは場の波動をしっかりと自らのタクトにひきつけなくてはならない。
自分の世界にしっかりと腰を据えて、その不動なる確固とした存在力でコンダクターが前に立つとき、場は瞬時に醸し出すリズムを感じとるだろう。
ドイツの指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラーは、楽団員に「立っていてくれるだけでいい」と言わしめたという。
存在そのものが場の規律を保ち、緊張感を高め、一体感を生み出す。朝比奈はそれをまさに、指揮者とオーケストラの理想の姿であると語っている。
「開かれた集中力」
コンダクターのシャーマン性とは、孤高なる存在感である。
時として場や空間をも、自分の世界に巻き込むエネルギーを内包した肉体であり、精神である。
プレイバック・シアターではこのシャーマン性が、強く強調されることがある。
コンダクターが場のざわつきや、落ち着きのなさを感じるとき、自分の軸がズレている、あるいは軸を感じ取れなくなっていることが少なくない。
「雨降らし男」のエピソードは、河合隼雄が心理療法の理想像としてあげている(*5)が、コンダクターのシャーマン性にも共通するメタファーである。
中国のある地方で数ヶ月間雨が降らず、困った村人たちは「雨降らし男」を呼んだ。
すると彼は小屋を作らせ、そこに籠もること3日間。その翌日の4日目に雪の嵐が生じ、村人たちは大いに喜んだ。
後日その理由を問うと、「ここでは天からの秩序によって人びとが生きていない。自分はここに来て自然の秩序に反する状態になってしまったので、もとの状態に戻るのを待った。すると自然に雨が降った。」と説明したという。
そこに因果関係はなく、あくまでも「自分がもとの状態に戻った」ことと「雨が降った」ことはただ・・・共時的に生じたというのである。
コンダクターがその場の中でズレやざわつきをひとつの軸のしっかりしたものにしていくことは、まさしくその場にいることへの集中力である。
コンダクターは常にこの軸を確認し、調整する必要がある。
そのひとつの方法として、丹田を意識することで軸の感覚をつかむことができる。
丹田は、「からだの中心」、また「気の場所」ともいわれ、人のからだを支える大事な部分とされている。腹が立つ、腹のそこから笑うという言い方があるが、この「腹」ではないかと思う。
自分の軸と同時にその場がもつ集団の軸を感じとる。
それは自分が開かれた状態でありながら、開かれた自分として集中しているということだと羽地はいう。
コンダクターは集団に対して、個人に対して、場に対して、いくつもの感覚に開かれていなくてはいけない。
そしてなによりも自分自身に対して、まっすぐ耳を傾けなくてはならないということである。
五感のバランス
以上、コンダクターがもちあわせる5つの要素を、いくつかの視点から述べた。
これらを「五感」としたのは、それぞれ頭で考えるというよりは、肉体に、精神にその感覚を巡らせるものであるように思えるからだ。
空気を感じとり、目で見てしっかりとアイコンタクトをとる。
語る言葉の内なる声を聴き、その心に触れ、ストーリーを味わいながら描いていく。そしてこの5つの感覚は、5つの役割をつなぎとめている。
プレイバック・シアターはなにものにも影響されない、影響しないといった第三者の存在がない。
テラー、観客、ストーリー、アクターそしてコンダクターは、居合わせるすべてのものに影響を与え合っている。
(*図2)ストーリーはテラーからコンダクターへ、そしてアクターを通って、観客を通って、みんなのところを回ってまた、テラーへと戻される。
ストーリーはその間を隈なく駆け巡り、新しいストーリーに浄化されて返ってくるのである。どの役割が欠けても、プレイバック・シアターは成り立たないのである。
もし観客がストーリーを「つまらない」と感じてしまえば、ストーリーはそこで滞ってしまう。
またアクターとコンダクターの間に信頼関係が成り立っていなかったとしたら、心から委ねることはできないだろう。
そして、コンダクターとテラーの間に不信感があっても、真のストーリーは紡がれない。
プレイバック・シアターは一体感や安心感を生む一方で、だからこそ相互の関係がどこかひとつ断たれてしまってもその共同体性を失うもろさを同時にもちあわせている。
この相互関係が潤滑に流れていくために、コンダクターは偏ることなく、この「五感」のバランスをとりながら、まさしく場をつなげていくのである。
日本大学大学院芸術学研究科 博士前期課程舞台芸術専攻提出
| 


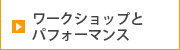
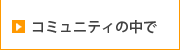
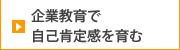

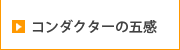
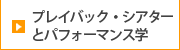
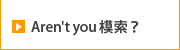
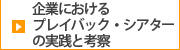
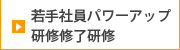
![]()

