プレイバック・シアター 語るなかで育まれるもの
■はじめに
語る場。プレイバック・シアター(playback theatre)をひとことで表すと私はこう表現する。もしくは「分かち合いの場」。誰かが語ったストーリー(自分が経験した出来事)を即興の劇で表現し分かち合う。プレイバック・シアターの構造はいたってシンプルである。
しかしこの一見単純で分かりやすい場で実は豊かで奥深いことが起こっている。
そして構造がシンプルなだけに実際の展開方法は様々であるが、その根底において「語る」「分かち合う」ということが常に大切にされている。人がストーリーを語り、分かち合うこと、それそのものがプレイバック・シアターの本質と言ってもいい。
私はプレイバック・シアターを病院臨床、教育現場、福祉施設など様々な領域で実践している。
特に精神科クリニックでの10年間の経験から、「語る、分かち合う」というプレイバック・シアターの基本を忠実に行なうことによって、参加した人たちの中に何かが育まれ、回復に役立っていることを実感している。(※1)
本稿では、ストーリーを語ることにどのような意味があるのか、分かち合う時にどんなことが起きているのか、という観点でプレイバック・シアターの実際について述べてみたい。
その為にはまず、プレイバック・シアターとは何かについて説明することにしよう。まだこのメソッドについて知らない読者がほとんどだと思うので。
■1.プレイバック・シアターとは
- 脚本のない演劇(non-scripted theatre) –
プレイバック・シアターは創始者ジョナサン・フォックスの「コミュニティの中で人と人のつながりを育む場」というアイディアから生まれた即興劇の一形態である。
試行錯誤の末に現在の形のプレイバック・シアターが1970年代中頃に確立され、今日ではジョナサンの精神を受け継ぎ、社会活動、教育、福祉、医療、芸術、エンターテイメントなど世界中の様々な分野で実践され発展している。
プレイバック・シアターと同様、脚本のない演劇メソッドとしてはサイコドラマとアウグスト・ボアール(Augusto.Boal 1931~)の被抑圧者の劇場(TO:Theatre of the Oppressed)がある。ジョナサン自身も影響を受けたと述べている(※2)このふたつの手法と比較してみると、プレイバック・シアターの特徴が明らかになってくる。
|
図1 サイコドラマ、プレイバック・シアター、被抑圧者の劇場
|
| サイコドラマ | プレイバック・シアター | 被抑圧者の劇場 | |
| 創始者 | J.L.モレノ 1889~1974 |
J.フォックス 1943~ |
A.ボアール 1931~ |
| 進行者 | ディレクター 指示する人 |
コンダクター つなぐ人 |
ジョーカー 演出家 |
| 主人公 | プロタゴニスト(主役) 本人が演じる |
テラー(語り手) 本人は語る、観る |
スペクタクター(観演者) 全員が観て、演じ、参加する |
| アプローチ対象 | 個人 | コミュニティ |
コミュニティ |
| 扱うテーマ | 個人の主観 (個人の問題) |
個人の主観 (人生で経験したこと何でも) |
コミュニティのテーマ |
| ねらい | 個人の問題解決 | コミュニティづくり | コミュニティの変革 |
まずサイコドラマとプレイバック・シアターは個人の主観を扱うという点では共通している。
しかしサイコドラマは対象となる主役個人の問題解決をねらいとした科学的手法として確立されているのに対し、プレイバック・シアターはコミュニティの中での対話の手段であり、問題解決や答えを得ることをねらっていない。
ジョナサンは「プレイバック・シアターは答えを求めない代わりに、深い対話の手段となります。そしてそこには人々の知恵がうつしだされているのです」と述べている。(※2)構造面での違いははっきりしている。
サイコドラマでは主役が自分自身を演じるが、プレイバック・シアターでは本人は語り手としてストーリーを語り、演じられる劇を見るだけである。役者がストーリーを舞台で演じ、そこには語り手・観客が入り込む事はない。
TOとプレイバック・シアターは、どちらも社会(コミュニティ)に何らかの影響を与えることを最終的な目的としている。
しかしTOは社会の問題を直接解決することをねらいとしている。個人の経験から社会の問題をあぶりだし、劇を発展させ、社会の変革を演劇を使って行なう。したがって個人の経験を、その本人のものとして掘り下げることはしない。
一方プレイバック・シアターはその人の人生の一片としてストーリーを扱い、それを大切にすることを通して、コミュニティの中で生きているひとりひとりを認め合う価値観を共有する。
構造として見ると、TOは参加者の誰もが自発的に劇に飛び込むことができ、「自分ならこうする」といったアイディアを出し合って、全員で問題解決のプロセスに参加する。
そしてプレイバック・シアターとサイコドラマ&TOは扱うテーマに大きな違いがある。
問題解決を目的にしているサイコドラマやTOは問題となる苦しみ、悲しみ、怒りをテーマとして扱うのに対し、プレイバック・シアターは、これらのテーマと同じぐらい、楽しい出来事や喜び、将来の夢や何気ない日常のひとコマがストーリーとして語られる。
※ジョナサンはサイコドラマの創始者J・L・モレノとザーカ・モレノ夫人とは交流が深く、モレノが亡くなる1年前にモレノ研究所でサイコドラマの研究を始めている。またザーカ・モレノはプレイバック・シアター誕生前の時代から現在にいたるまでジョナサンに多大な援助を与えており、ビーコンハウスの一室をプレイバック・シアターが誕生する前の経済的に苦しい時代に無料で一年間貸し出している。
※プレイバック・シアターを創りだす初期の頃に、ボアールの著書「被抑圧者の劇場」(※3)とパウロ・フレイレ(Paulo Freire 一九二一~一九九七)の著書「被抑圧者の教育学」(※4)に強く影響を受けたとジョナサンは述べている(※2)
ブラジルの教育学者フレイレは1950年代後半からラテンアメリカにおける貧しい民衆に文字、言語の必要性を説き、貧困層の「意識化」(=与えられたものの中で漠然と生かされている世界から意識をもって生きることを目的とした識字教育法)を実践した。
特に1973年フレイレ指導のもとペルーで行なわれたALFIN(総合識字計画)では、「演劇や写真は総合して自分の言葉を持つ」として、積極的に芸術部門を取り入れるなどユニークな活動を行なった。その演劇部門に招かれたのがボアールであり、言語としての演劇=被抑圧者の演劇を形成していった。
– ストーリー –
プレイバック・シアターでは、その場で語られた人生のある出来事や日々の生活のひとこまが即興で演じられる。
演じるのは、日頃から練習をつんだ役者たちが行なう時もあれば、まったく演劇などとは無縁な初心者の参加者が役者となる場合もある。どちらにしろ大切なのは、あくまでもストーリーを語った語り手の為に、役者は精一杯演じる、という点である。
役者自身の自己表現や観客をわかす為の劇では決してない。
その場を司るコンダクターは語り手の話に耳を傾け、役者は委ねられたストーリーに敬意をはらいベストをつくす。このようにして即興で劇が生まれでるプロセスを全員で見守る。
即興という、創造と集中に満ちあふれた舞台で語り手の人生が再現される。
そして自分自身の人生が再現されるのを語り手本人も舞台上の席で見つめる。観客にとっては、語り手の表情の変化や、後戻りできない即興空間で失敗を恐れず精一杯表現する役者の姿も、舞台上で繰り広げられるドラマの一部となる。
私はこのプロセスをこれまで何度も見ているが、皆の前で自分の人生のひとこまをオープンにする語り手の勇気と人々に対する信頼、自己防衛を乗り越え失敗を恐れず演じる役者たちの誠実さ、そしてさっきまで自分たちの隣人だった語り手と役者を温かく見守る観客の寛容さに、毎回心うたれる。
プレイバック・シアターでは、よく「全員が何かを差し出している」と表現されるが、その場にいる全員に「自分もこの場を支えている」という意識が共有されると、場全体の一体感が育まれてくる。見方を変えると、勇気を持ってストーリーを語る語り手を支える為に、人々のつながりが生まれるのである。そしてストーリーが語られ演じられ、全員の一体感が深まり、また次の語り手が手をあげる。
|
図2 プレイバック・シアターの構成
|
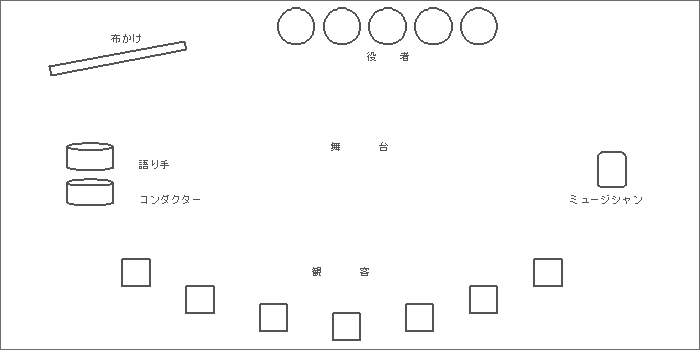
初心者に即興で演じる劇などできる訳が無い、できたとしても底の浅いものであろう、と思う人もいるかもしれないが、場の一体感が深まり安心感が生まれると、人前で演じた経験のない人でも創造的な表現ができる。
そして初心者であろうと熟練した役者であろうと、語り手への敬意と誠実さがあれば、語り手の気持ちをくみ取った奥深い劇ができる。
かえって初心者の邪心の無いたどたどしくも精一杯の表現に、語り手や観客が強く心動かされることがよく起こる。
どちらにしろ、場の一体感とお互いへの敬意から、創造性と感性豊かな劇が生まれ、その劇に人々が心動かされ、一体感が深まってくるのである。
先に観客をわかす為の劇ではないと述べたが、役者が語り手の為に誠実に舞台上にいる姿が結果として観客の心を動かす。このようにして結びつきが深まった場では、その深まりに応じて語られるストーリーのテーマも深まってくる。
– コンダクター –
これまで述べてきたプレイバック・シアターの効果的側面は、その場の一体感、信頼感がないと生まれない。
そして不安定な中ではその良さが発揮されず、安心感もなかなか育まれない。プレイバック・シアターが成り立つかどうかは一体感・信頼感を創りだせるかにかかっているが、そこが一番難しい。この場づくりをリードするのがコンダクターである。
プレイバック・シアターでは全体をリードする人をコンダクター(conductor)と呼んでいる。
オーケストラの指揮者とイメージが重なるし、「conduct:つなぐ」という意味もある。コンダクターは観客と役者、語り手をつなぐ役割を担っている。進行者をサイコドラマは「ディレクター:指示する人」、TOは「ジョーカー:演出家」と呼んでいるが、その呼び名がそれぞれの手法のリーダーのあり方を象徴的に表していて興味深い。
コンダクターの役割はふたつに大別される。
ひとつは集団全体の運営者、つまりファシリテーターとしての働きかけである。私はこれを広義のコンダクティングと呼んでいる。
ここでは語り手が安心してストーリーを語る事ができ、役者が創造的かつ誠実に表現ができる場を創ることが求められる。
そしてもう一つは、そのような安定した場の中で語り手と対話をし、ストーリーを紡いでいく働きかけで、それを狭義のコンダクティングと呼んでいる。この狭義のコンダクティングのプロセスにおいて、実際に語り手のストーリーを聴いている時間はわずか数分だが、この段階はコンダクターにとって最もスキルと集中力が必要とされる。
語り手のストーリーを聴いている時のコンダクターのあり方は、ストーリーの世界を語り手と共に歩む、そんな感じである。
辛く苦しい経験の世界を共に歩む時は、語り手が選んだ道を一歩一歩確認しながら、横に寄り添い行きつ戻りつする。語り手が楽しかった思い出を見てみたい場合は、その場面を一緒にワクワクしながら同じリズムで経験する。
何気ない日常生活の一場面のストーリーは、一緒にしみじみと味わいながら歩む。
コンダクターは語り手の話を分析的にきいたり批判や解釈を決してしない。共に歩むコンダクターの横でストーリーを語り、そしてそれが誠実に演じられ、観客に受けとめてもらうことで、語り手はその場の全員から大切にされ、ストーリーはまた語り手の元に返される。
この経験を通して語り手の中に何かが育まれる。
– 桜の木の下で –
私の勤めるアルコール依存症治療専門病棟でのプレイバック・シアター。
私のプレイバック カンパニー(劇団)のアクター達が手伝いに来てくれて、集団療法室の一角に設けられた舞台に立っている。
「この劇はプレイバック・シアターといって、私たちの思い出を見る事ができます。昔のことでも最近のことでも、苦しかった出来事、楽しかった出来事、何気ない人生のひとこまなど、見たい場面のある人、よかったら手をあげてもらえますか?」
私が促すと沈黙が続き、しばらくして手をあげたのはAさん。
強面の元やくざの彼が手を挙げたのに少し驚いたが正直嬉しかった。刺青が袖口から覗く彼は「退院したら俺は酒を飲む」と公言していて病棟では扱いにくいと厄介者扱いされている。が、私は彼の筋を通すところが好きで、彼も私にはどこか心をひらいている感じがしている。
彼が語ったストーリー。
先週病棟行事で○○公園に行軍で行った時、散り始めの桜がきれいだった。配られた弁当を食べようとしたら、どこかの老人ホームのおばあちゃんおじいちゃん達も来ていて、「どこから来たの、一緒に食べよう」と声をかけてくれた。俺たちは桜の木の下でおばあちゃんおじいちゃん達と一緒に弁当食べた。食べ終わったら一緒に歌うたって踊った。楽しかった。あんなに笑ったのは久しぶりだった。
劇が始まる。
桜の木を演じる役者が椅子の上でピンク色の布を優雅にたなびかせ、その下で本人を含めた病棟の仲間とおばあちゃんおじいちゃん達が笑いながら踊る。語り手の席でAさんは照れくさそうに笑いながら劇を見る。
劇が終わり、Aさんに感想を求めると「そう、こんな感じだった。楽しくて腹抱えて笑った。酒飲まないであんなに楽しかったことは、これまでなかった。飲み仲間以外の人と笑って話している自分を見て、不思議だけど嬉しい」
■2.語ること
– ナラティヴ・アプローチ –
プレイバック・シアターは「語り分かち合う」ということを大切にしているが、そこにはふたつの側面がある。
ひとつは語り手はコンダクターとの対話の中で語るという点。もうひとつは、語り手は観客が見守る中で語り、劇を通してストーリーをその場の全員で分かち合う、という点である。
前者において、コンダクターが語り手とどのようなかかわりをして、そこに何が起きているのかを考えるうえで、私にはナラティヴ・アプローチの概念が役にたった。それについて述べてみたい。そして後者については、「分かち合う」ことの意味を身を持って学んだ私自身の経験を後に紹介したい。これが私のプレイバック・シアターのスタイルを確立するうえでの原点にもなっている。
– 無知の姿勢 –
プレイバック・シアターのコンダクターと語り手のかかわりは、ナラティブ セラピーのセラピストとクライエントのかかわりと重なるところがある。H・グリーシャンとH・アンダーソンは、セラピーを「語り、物語、会話の思いがけない展開のなかにのみ存在するもの」と述べている。
(※5)このアプローチにおいてセラピストに必要なのはクライエントの問題を解決しようとする姿勢ではなく、「無知の姿勢」であり、その「無知の姿勢」からの質問によって「クライエントの生きる世界」が語られ、クライエントに変化が生じる。「無知の姿勢」とはセラピストの「話されたことについてもっと深く知りたいという欲求」のあらわれで、つねにクライエントに「教えてもらう」立場のことである。
(※5)この「無知の姿勢」は、オーストラリアのプレイバック・シアターの実践者 メアリー グッドの「純粋な探求者」(※6)の姿勢と同じ立場であり、グリーシャンらのアプローチとプレイバック・シアターのコンダクティングのプロセスとは根本的な価値観の部分で共通している。
この「無知の姿勢」で聴くことが狭義のコンダクティングでは大切なのだが、これが最も難しいところでもある。
つい我々は客観的な意見、専門家の立場でのアドバイスを言いたくなってしまう。もちろんコンダクターは必要な時は自分の意見を伝えるが、この姿勢でかかわりを築くことが前提となる。
そして矛盾しているようだが、「無知の姿勢」でかかわりながら、コンダクターの直感は「なぜ語り手はこのストーリーを、今ここで語るのだろう」「このグループにとって、このストーリーにはどのような意味があるのか」ということを、どこかで自問自答している。コンダクターの決断は直感に委ねられている。コンダクターは自分の内なる声にも耳を傾けている。
もともと治療技法ではなく、コミュニティにアプローチする演劇として生まれたプレイバック・シアターが治療効果を生みだすのは、ナラティヴ セラピーの構造を持っているからであり、この点をおさえることが、治療現場の実践上重要な点である。
– 経験と自己概念 –
語り手は、プレイバック・シアターの中でストーリーを語り、そのまま受けとめてもらう経験をすることによって、その場全体から影響を受ける。それによって語り手の経験の枠組みが変わり、新しい自己概念を生みだす。
私たちは、たくさんの経験を積み重ねて今の自分がいる。
この世にふたつとない「私」の経験をしてきたからこそ私は「私」なのだ。ここでの経験とは主観的な、自分の内的世界での体験のこと。
これまでも、そして今現在も、私たちはそれこそ無数の経験をして自分を生きている。そのような経験ひとつひとつが現在の自分を構成している。
「私はこんな人」といった自己概念もこの経験を基に形づくられている。
例えば誰からも理解してもらえない寂しい経験や、周りの人から大切に扱ってもらえない経験からは、「私は誰からも愛されない人」という自己概念が生まれ、一旦これが形成されるとあらゆる出来事が「誰からも愛されない」と経験され、自己概念をより一層強化する。
病院臨床のグループセラピーでは、このような否定的な自己概念でがんじがらめになって苦しんでいる人に出会うことが多い。彼らはグループが安全だと分かると語り手として手を挙げ、ストーリーを語る。
長年囚われていたストーリーを語り、劇として見る。
こうしたプロセスの中で、「誰からも愛されない私・誰からも理解されない私」がみんなから受けとめてもらう経験や、劇を見て心動かされた観客の共感や賞賛をもらう経験をすることで、「人から理解され、共感される私」という新しい自己概念が芽生える。集団の中で受けとめてもらうことも、治癒力を生み出す要素のひとつとなる。
臨床現場で行なうにしろ、地域社会で行なうにしろ、プレイバック・シアターで語られるストーリーは苦しみだけではなく、嬉しい経験、驚いたことなど様々である。どのようなストーリーでも、自分の経験を語り、それが表現され分かち合われることに意味がある。
先に述べたように私はここに興味がある。
なぜ人は自分の個人的な経験を語るのだろう。ストーリーを語ると何が生まれるのだろう。語る事が本人だけでなく、グループにも影響を与えるのはなぜだろう。プレイバック・シアターの本質もここにあるように思う。
ピーター・ブルックの演出で戯曲にもなった「妻を帽子とまちがえた男」の一節に、コルサコフ症候群で自分が体験していることを数秒間しか覚えていられない男が登場する。男は常に自分のストーリーをつくりあげ、語り続ける。失われていくものを埋めあわせるために、たえず周りの事や自分のことについて作り話を続ける。
われわれは、めいめい今日までの歴史、語るべき過去というものをもっていて、連続するそれらがその人の人生だということになる。
われわれは「物語」をつくっては、それを生きているのだ。物語こそわれわれであり、そこからわれわれ自身のアイデンティティが生じると言ってもよいだろう。
(中略)
われわれは「自分」であるためには、「自分」をしっかりもっていなければならない。つまり自分自身の物語というものをもっていなければならないのである。必要とあらば、あとから所有するのでもいい。
これまでの自分についての物語、内面のドラマというものを、回想してでももつ必要がある。それがないことには、自己のアイデンティティはない。「自分」は見失われてしまうのである。 オリバー・サックス「妻を帽子とまちがえた男」(※7) AA(Alcoholics Anonymous)
分かち合いの場としてのプレイバック・シアターのスタイルを確立するうえで、私はアルコール依存症の自助グループAAから強く影響を受けている。現在私はアルコール依存症治療専門病棟で週に一回治療グループを担当している。この病院の仕事を始める前に3ヶ月間AAミーティングに通った。
ちょうど十年前の年始めのことで、前職を辞め何も仕事が無い時期。
4月から週1回グループを担当することになっていたが、それまで特に仕事もなくやることのない私にある人が「アルコール依存症をやるんならAAぐらい知らないと」と家から歩いて行ける横浜寿町のAAを紹介してくれた。
「僕はアルコール依存症ではないけれど、参加していいか」とお願いしたら、いいよと受け入れてくれた。
初めて緊張してミーティングに参加して、強い衝撃を受けた。参加している人の強烈な個性もさることながら、ミーティングが始まると順番に自分の過去の飲酒体験や現在の心境が語られた。すさまじい内容にもかかわらず語り口は淡々としている。そして語る人以外はただ黙って聴いている。
話の内容と雰囲気にただ圧倒されて、自分の番が来ると「パスします」とだけかろうじて言ったのを憶えている。
終ってチェアマンにお礼を言い会場を出た後、呆然とした頭の中でふたつの事が錯綜していた。驚きと疑問。驚きは、ただ自分の体験を語るだけ、それを人々は聴くだけ。それ以外に特別な事は何もしない。
なのに強いインパクトがあり、そして参加者にとってはまるで教会のミサのごとく精神的支柱になっている。
ドヤ街でのミーティングだったこともあり一見して只者ではない人たちが、指示されることもなく自発的に動いてこの場の秩序を大切に守っていた。そこには進行役のチェアマンはいるが、コントロールする側される側の上下関係がなく、全員が対等でありながらどこか儀式的な秩序が保たれている。自分がこれまで知っているグループとはまったく違ったものだった。
しかしもう一方で冷静になって考えると、語るだけで何の意味があるのか、何を目的にしているのかよく分からないという疑問が残った。
この疑問の根底には、自分のことを何も語らなかったことへの引っかかりがどこかであった。よく分からないながらもしばらく通い続けるうちに、知り合いも増えてリラックスして参加するようになった。
そして初めてパスせずに、失業中の自分の気持ちをミーティングで語った。
朝起きて何もする事がない焦り。布団の中できく通勤する人々の靴音。誰からも必要とされない疎外感。
語り終わると聴いていたメンバーがいっせいに拍手をしてくれた。えらい嬉しかった。なんだかじわっときて、みぞおちのあたりからすっと何かが落ちた感じがした。
これまで誰にも言わなかったことを語り、それを聴いてくれて拍手までしてくれた時の嬉しさ、受容された感じ、みんなに対するありがたさ。この経験は私に語ることの大切さを十分に教えてくれた。
語ること、分かち合い、対等、儀式性と秩序、自発性、お互いの敬意。私がプレイバック・シアターの中で大切にしていることは、AAから学んだことばかりである。
■3.コミュニティの中で
– ネパールでの体験 –
病院や自助グループなどの限定された人々によって構成された閉じたグループでのプレイバック・シアターについて述べてきたが、本来はコミュニティに開かれ、対話を通して人と人のつながりを育む場として生まれたものである。
それを象徴するエピソードとして、プレイバック・シアターを創りだす原型となったジョナサンのネパールでの体験がある。
彼はハーバード大学卒業後ピース コープス(日本の海外青年協力隊のようなもの)の一員としてネパールの農村で2年間過ごした。
そこでは、定期的に村人が集いお互いに語り合う儀式的な場があった。
語られる事は、先祖からの言い伝えや祖先の神話、生活の中の出来事、家族を失った悲しみ、近隣の村での出来事など様々であった。人々はここで共に喜び、悲しみ、驚き、そして生きていく智恵を代々受け継いでいた。そうすることでコミュニティの一員としてのアイデンティティを確立していたのであろう。
正にこの場が、共に生きていく人々のコミュニティ(共同体)を育んでいた。既に文明社会では失われつつあるこのような場に、ジョナサンは長く探し求めていたものを見いだしたのである。
– 校長先生のストーリー –
地域社会でのオープンなプレイバック・シアターについて紹介する。
このようなオープンな場では、地域に住む隣人同士が非日常の場で日常のストーリーを分かち合う。コミュニティの中で日常と非日常がつながりながら存在することについては後に述べるとして、子どもと大人が不思議な空間でワクワクする体験を一緒にする、それだけで素敵なことである。
校長先生のストーリー
私のふるさと沖縄のN小学校でのプレイバック・シアター。
教育委員会主催の催しで、地域の人は誰でも参加できる。校舎の広いスペースにブルーシートを敷きつめて観客席をつくり、体操用マットを六つつなげて舞台にする。準備完了。
ところが開始時刻になっても観客席にはほとんど誰もいない。
30分過ぎた8時頃になって、ようやくぞろぞろとみなさん集ってきた。沖縄タイムとはこのことだ。観客席の前の方に陣取った子どもたちからは石鹸の香りがする。夕食とお風呂をすませてきたのだろう。
50人ぐらいの大人や子どもが集り、ようやく始まった。
簡単なプレイバック・シアターについての説明の後はゲームをやりながら徐々にリズムをつくる。笑い声と好奇心いっぱいの子どもたちの目。創造性と安心感が徐々に溢れてくる。こうなったら大丈夫。ストーリーをやろう。
語り手を募ると子どもたちが次々と手を挙げる。
家族でビーチに遊びに行き、兄弟でバナナボートに乗り楽しかった。ピアノの練習を一生懸命やって、緊張したけど発表会でがんばって弾いた。どれも大切な出来事。
あっと言う間に時間が過ぎ、最後のストーリー。
役者をやりたがる子ども達とスタッフの役者たちが舞台上に並ぶ。手を挙げたのは校長先生。貧しかった子どもの頃のストーリーを語った。
遠足の時にお母さんがお弁当をつくってくれた。びっくりするようなごちそうばかりで、もったいなくて食べられなかった。お母さんにも食べてもらおうと残して持ち帰った。
テラーズアクター(語り手役の役者)に選ばれたのは一番活発に参加していたY君。
姿勢よく舞台に立ち校長先生が語るのをしっかりと聴き、感性豊かに堂々と演じた。他の役者との呼吸もぴったりと合い、母を想う少年の気持ちが見事に再現された。
見終わった校長先生が「嬉しい、この通りだった。あの子は僕の気持ちをよくわかってくれた」と、演じた生徒を見る目が潤んでいる。大きな拍手の中、役者の子ども達と語り手の校長先生が観客席に戻る。
校長先生の為に子どもたちが物怖じせず一生懸命演じてくれた。日常の「先生 教えるー生徒 教わる」という関係と違ったかかわりがそこにはあった。
コミュニティの中でオープンなプレイバック・シアターを行なうと、いろいろなことが起こる。
ひとつは、日常で関係のある人同士の、いつもとは違った関係性のかかわりがある。そして、コミュニティの中で非日常的時間を共に過ごす。つまり祭りや土着の儀式のようなものである。
もともとは、どこにでもこのような祭りや儀式はあった。
そこで人々のつながりやコミュニティの一員としてのアイデンティティが育まれ、そして社会で生きていく為の様々な事を学んでいた。(※7)時に悩みや問題もこの非日常的時間を共に過ごすことで昇華されていたのではないだろうか。
– 最後に –
私は様々なところでプレイバック・シアターを行なっているが、病院臨床であろうと子ども達と地域で行なう時であろうと基本的にやっていることに変わりはない。共にいて、安心感の中で語り分かち合う。そうすることで新しい自分が生まれる。そしてグループの中で支えられ、他の人を支えることによって、社会で生きていく力を身につける。
|
図3プレイバック・シアターの実践領域
|
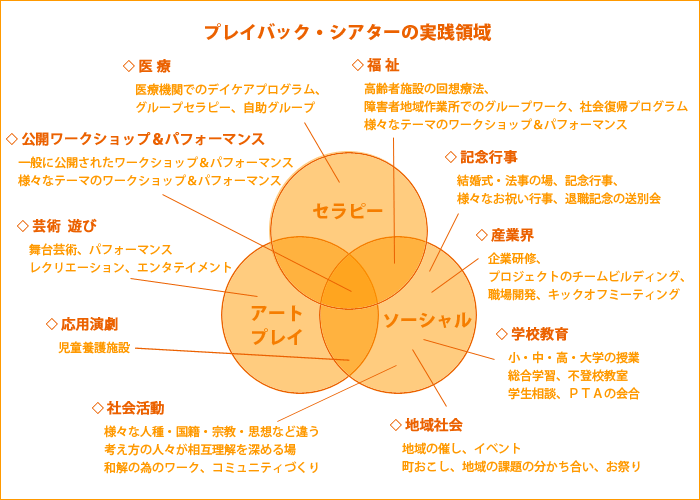
最後に「プレイバック・シアターの実践領域」を添付した。
現代社会は医療、福祉、教育、地域活動、ビジネス活動、芸術等が区分けされて存在している。それぞれの領域が高度に専門化され、専門家が担当し、他領域とのつながりはほとんどない。
社会で暮らす我々も、子どもは学校、大人は会社、老人は高齢者施設、病人は病院、障害者は障害者施設と区分けされ、隔離されている。
この区分けされた社会の中で、プレイバック・シアターは縦横にいろいろなところを行き来する。
分断されている人と人を結びつけ、社会のつながりを育んでいる。これからも布と楽器をひっさげて、いろいろな人たちとプレイバック・シアターを行いたい。
![]()
– 引用文献 –
※1 諸江健二 羽地朝和
『自己のナラティヴ(物語)を観ること-プレイバック・シアターによる効果の考察-』心理劇研究 第26巻 第1号 2002 8-15
諸江健二 羽地朝和
『一体感が生み出す物語の連鎖―プレイバック・シアターによる治療の効果―』,心理劇 第9巻 第1号 2004 69-80
平田、諸江、羽地
「僕のストーリーが生まれたよ クリニックに通う子ども達とのプレイバック・シアター」 日本心理劇学会第9回大会(2003)にて発表
※2 school of playback theatreホームページより http://www.playbackschool.org/about_comparison.htm
※3 Augusto Boal, THEATRE DE L’OPPRIME,1975(アウグスト・ボアール 里見実、佐伯隆幸、三橋修訳『被抑圧者の劇場』晶文社 1984)
※4 Paulo Freire, PEDAGOGIA DO OPRIMIDO,1970 (パウロ・フレイレ 小沢有作他、楠原 彰、柿沼秀雄、伊藤周訳『被抑圧者の教育学』 亜紀書房 1979)
※5 野口裕二 物語としてのケア ナラティヴ・アプローチの世界へ 医学書院 2002
※6 Jo Salas, Improvising Real Life:Personal Story in Playback Theatre,1993(ジョー サラ 羽地朝和監訳 『プレイバック・シアター 癒しの劇場』 社会産業教育研究所)
※7 オリバー・サックス 高見幸郎、金沢泰子訳 『妻を帽子とまちがえた男』晶文社 1992
※8 羽地朝和『コミュニティの中で プレイバック・シアターの実践を通して』心理劇 第八巻 第1号 2004 619-23
参考文献
※ Jonathan Fox. Acts of service Spontaneity,Commitment, Tradition in the Nonscripted Theatre.1994.Tusitala Publishing
※ Jonathan Fox & Heinrich Dauber,Eds. Gathering Voices Essays on Playback Theatre.1999.Tusitala Publishing
※ 太田華子 プレイプレイス~プレイバック、インプロを活用した学校教育へのアプローチ 演劇創造34 2005 日本大学芸術学部演劇学科 150-161
※ 葛西李奈 Aren’t you模索?~はじめてのプレイバック・シアター~演劇創造34 2005 日本大学芸術学部演劇学科 162-167
(はねじ ともかず プレイバック・シアター研究所所長)
